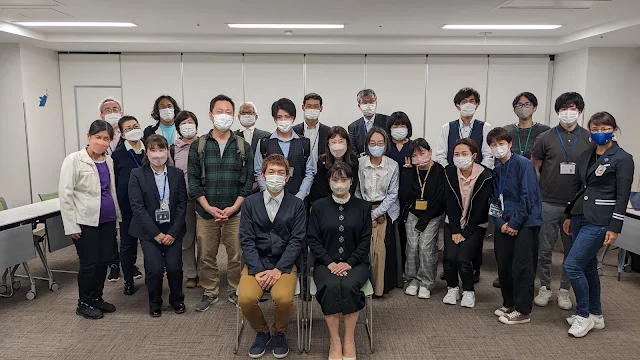アンケートでいただいた回答を、講演をしていただいた講師の方にお答えいただきました。
お答えいただいたのは・・・・
一般社団法人日本発達療育士協会 代表理事 奥田幹子氏
株式会社こども未来研究所 代表取締役 高瀬彰子氏
質問1:偏食の児童は、99.9%は成長とともに感覚も成長して食べられるようになるとのことでしたが、残りの0.01%のケースの場合はどうすればよいのでしょうか?
回答:偏食、0.01%のケースは、元気であれば、神経質にならずで大丈夫です。食べれるものを食べてください。ただ、健康を害しているのなら、医師への相談が必要となります。
質問2:便を拭けないので教え方とかあれば聞きたいです。
回答:便が自分でふけない理由は、潔癖、太っていてお尻が見えないから感覚が掴めない、見えない場所だから不安、拭く意図がわからないなど様々な原因があります。原因を見極めた上で、潔癖なら【ビニール手袋を使う、多めに紙を使う】、太っているなら【痩せる方法を考えるとともに、またから手を入れて拭く方法を一緒にしてみる】、見えなくて不安な場合は【一緒に手の置き方などを手を持って教える。実際にパンツの上からでいいので、やって見せて、頭の中でリンクさせる】、拭く意図がわからない場合は【図や絵で説明し、〇回拭く、紙に便がつかなくなるまで拭く練習を行う】などされてみてください。ウォッシュレットを使用するのも一つです。
質問3:肯定的な声掛けをしても反発される時があります。(「褒めないで」など)。小3男子なので、これを心の成長と捉えてそのままにしておいていいのか、他の声掛けなど何をすべきか、どう対応すれば「自己肯定感」につながるでしょうか?
回答:そのお子さんに響くジェスチャーで伝える褒め方や言葉の選択、声のトーンを試してみられてください。無理に褒める必要もないので、時期によって受け入れ方も変わってきます。自己肯定感を上げるには、褒められて反発してきても、ママは嬉しい、成長が見れて安心した事など、お母様の気持ちを伝えてあげる【Iメッセージ】が良いです。褒めるは、時にジャッジメントとなってしまいます。お母さんの嬉しかった気持ちや助かった気持ちを声に出してください。私が言いたい、伝えたいだけだからというスタンスで大丈夫です。認めてもらえている、自分はそのままでいい!と思えるようになります。
質問4:ASDで自分のやりたいこと以外はすぐに怒ってしまします。(受け入れに時間がかかる)怒らずに表現できるようになるにはどうしたら良いか。もう18歳なんです。
回答:自分で選択し決定するという経験を積ませてください。また、外出する時に、選択権を与える、嫌な外出が出来たときは好きな事を帰る前にさせてあげる、どうして怒っているのか直接聞いてみる、怒らず伝える方法や言い方を教えるなど、紙に文字や図、絵にかいて確認するとイメージが具体化されます。
質問5:お金の概念がむずかしい。数の入れ方を聞いてみたいです。
回答:実際に100円から自分の好きなお菓子を買いに行く、お買い物ミッションをする、チラシなどを利用して、電卓で合計金額を出しお金を使って支払いごっこをする、お釣りの読み方をその都度教えるなど、実体験を通して獲得していくことが必要不可欠となります。ご家庭でお手伝いアルバイトをして、お金を稼ぐ意図やその使い方を一緒に考え実践していくこともおすすめです。